今回は小説『母性』湊 かなえ著のご紹介。
「母性」と聞くとなんだか心温まるイメージ。
しかし、著者は湊 かなえさん。
心温まるイメージはどのタイミングで打ち砕かれるのでしょう?
書籍の情報を以下にまとめます▼
INFO
タイトル:『母性』
著者:湊 かなえ
出版社:新潮文庫
発売日:2015年7月1日(発行)
メモ:戸田恵梨香さん、永野芽郁さん主演で映画公開中
Amazonからの購入はこちら▼
こちらの書籍を購入した際の記事もご覧ください▼
あらすじ

女子高生が自宅の中庭で倒れているのが発見された。母親は言葉を詰まらせる。「愛能う限り、大切に育ててきた娘がこんなことになるなんて」。世間は騒ぐ。これは事故か、自殺か。・・・・・・遡ること十一年前の台風の日、彼女たちを包んだ幸福は、突如奪い去られていた。母の手記と娘の回想が交錯し、浮かび上がる真相。これは事故か、それともーーーーーー。圧倒的に新しい、「母と娘」をめぐる物語。
『母性』裏表紙より
読書感想
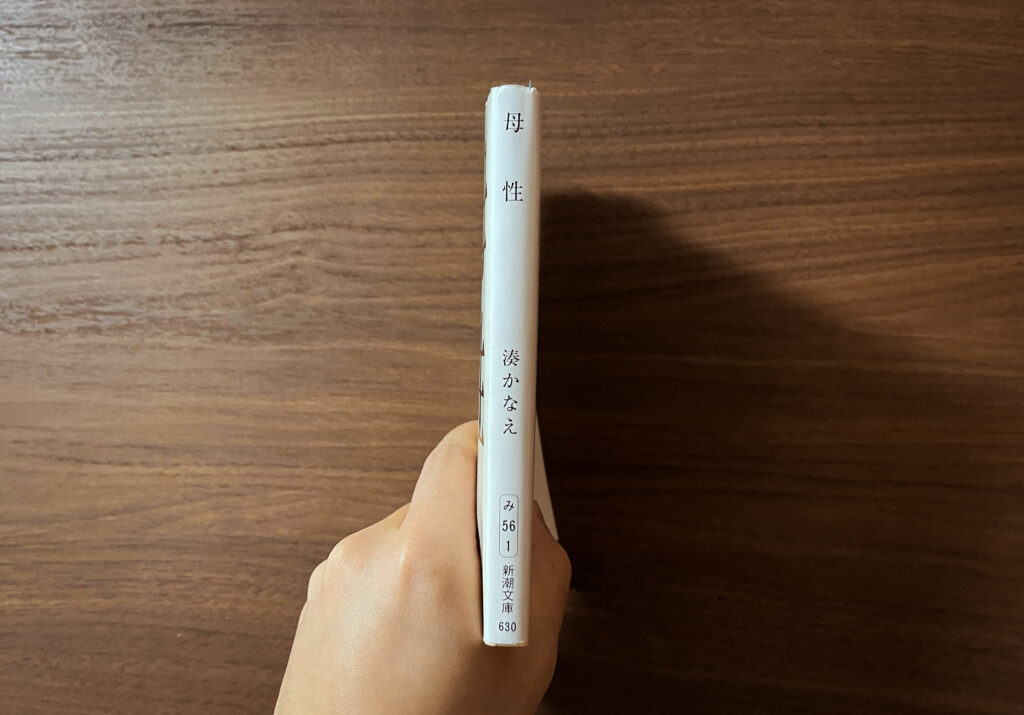
愛情のサイクル
赤ちゃんとして生まれた時、母親からの愛情を独り占めすることができる。
そして思春期を迎えた段階で1度その愛情を手放そうかと思う。
しかし、思春期を過ぎると母親の愛情は親近感を持って再度登場する。
「今度は愛情を与える側になりたい」
愛情は与えられるものではなく、与えるものでもある。
そうして人は大人へと成長していく。
人生において一方通行は存在しない。
今まで論じてきた通り、愛情も与えられ、そして与える。
愛情のサイクルはそうやって保たれてきた。
一方で、母親からの愛情にどっぷり浸かって抜け出せない人がいる。
自然と自らが愛情を与える姿というのをイメージすることができない。
どこか遠い国の話なのかと勘違い。
そのような人であっても異性との愛情はまた別の世界らしい。
自らの分身的存在である息子や娘を身籠る。
まさに、与える存在である。
しかし、愛情を与える姿がイメージできない人は、与える努力をしない。
むしろ、これまで母親から与えられていた愛情に特別感を抱く。
するとその人はまた、赤ちゃんへと戻るのである。
子供に求めてしまうもの
子育てをしていると忘れてしまうことがある。
それは、子供は自らの分身であることだ。
ついつい自分の子供には期待を抱いてしまう。
叶えられなかった自らの夢を子供に託すという親もいる。
しかし、勘違いをしてはいけない。
子供は自らの分身であることを。
どんなに泣き喚いても、どんなに言うことを聞かなくても、
そしてどんなに自らが求めるように成長してくれなくても。
その姿=私の姿であると認識しなくてはいけない。
子供に期待をしないという言葉は悲しく聞こえる。
しかしこれは、子供が親である自分を超えていくために重要なことである。
手塩にかけて育て過ぎると、自らのエッセンスが濃く出てしまうのだ。
すると子供は悪い意味でどんどん自分に似てくる。
「こんな子供に育てた覚えはない。」
それは自分に対する悲観的な叫びとなってしまう。
「母性」とはなんだろうか?
小説のタイトルにもなっている「母性」について。
「母」という文字が入っていることからも母親特有のものであるようだ。
対義語として「父性」という言葉も、もちろんある。
しかし、子育てにおいて「父性」という言葉の出番は限りなく少ない。
それだけ自らの体の中に命を宿し産むという行為は、特別なのであろう。
「母性」とは母親としての本能や性質を指し、本来持っているものとされている。
つまり、意識して身につけるものではなく、自然と身についていくものということだ。
しかし、十人十色という言葉がある通り、本来持っているとされている「母性」も
人によっては手に入れるまでに時間がかかったり、あるいは持てなかったりもする。
また、自分には母性がないと気が付ける人はいないだろう。
「母性」とはステルスである。
こちらが気づかないうちに、求めていることを陰で支えてくれている。
母親も別に隠れてやっているつもりはない。
自然と身についた母性を私たちも自然と求めてしまう。
それは当たり前のことであり、そこに母親と子の関係性がある。
私たちは見ることも、言葉で表現することも困難な母性を感じて成長してきた。
まとめ
今回は小説『母性』湊 かなえ著のご紹介でした。
子供を授かった女性は持って当たり前とされている「母性」も
言葉自体が曖昧で不透明な分、その習得は難しいものだと感じます。
小説「母性」はフィクションでありながら、同じような境遇にあっている人がいる。
そんなことを感じさせるくらい、リアルな描写があります。
Amazonからの購入はこちら▼




コメント