今回は小説『祈りの幕が下りる時』東野 圭吾(著)のご紹介!加賀恭一郎シリーズの10作目となります。
こちらは映画化された作品です。
本作品では、主要人物である加賀恭一郎の過去が明かされます。
書籍の情報を以下にまとめます▼
INFO
タイトル:『祈りの幕が下りる時』
著者:東野 圭吾
出版社:株式会社 講談社
発売日:2016年9月
メモ:人気の加賀恭一郎シリーズの10作目
あらすじ
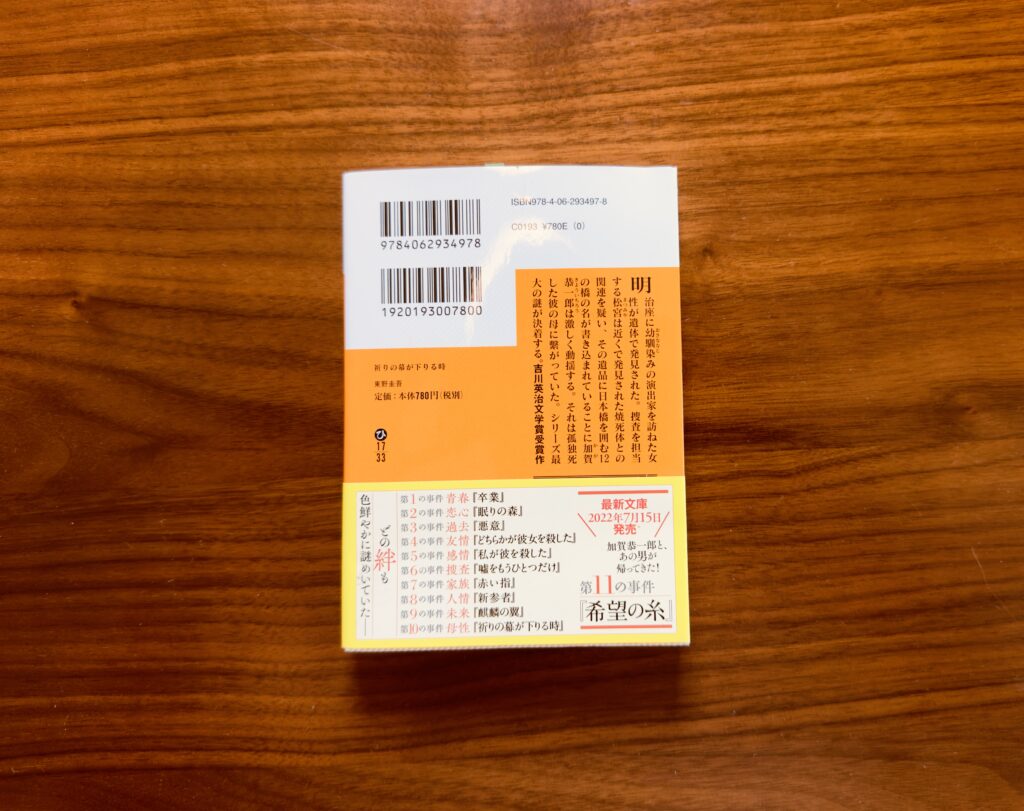
明治座に幼馴染の演出家を訪ねた女性が遺体で発見された。捜査を担当する松宮は近くで発見された焼死体との関連を疑い、その遺品に日本橋を囲む12の橋の名が書き込まれていることに加賀恭一郎は激しく動揺する。それは孤独死した彼の母に繋がっていた。シリーズ最大の謎が決着する。
『祈りの幕が下りる時』裏表紙より
読書感想
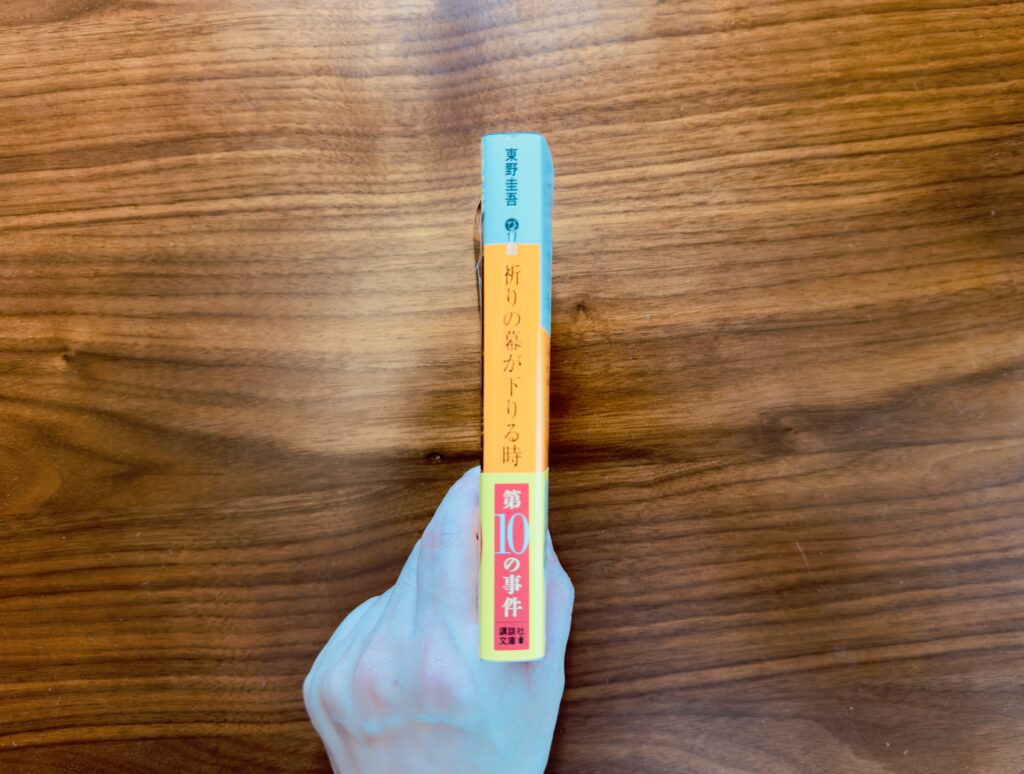
ナチュラルな悲劇
因果応報という言葉は、過去の行動が現在の幸・不幸を決定づけるという意味である。つまり、過去に悪い行いをすれば、それが将来の不幸に繋がるという考え方である。この言葉が示す通り、人間はいつ何時も良い行いを心がけるべきである。しかし、時として自分が悪いと感じていなかった行動が原因で、予期せぬ大きな不幸や悲劇が生じることもある。
これはまさに目を背けたくなるような悲劇であるが、「運が悪かった」と片付けるのは、当事者ではない周囲の人間に過ぎない。当事者にとっては、過去の行動が招いた結果に押しつぶされ、悔やんでも悔やみきれない気持ちに囚われ続けることになる。毎日のように過去を振り返り、自らの行いを後悔する日々が続くことだろう。
ここで考えさせられるのは、無意識で行ったことや、悪いと感じていなかった行動でさえも、因果応報の原理に飲み込まれてしまうのかということである。人は常に意識的に生きているわけではなく、何気ない行動が後に大きな影響を及ぼすことがある。このような現実を前にすると、私たちは自らの行動に対してより一層の注意を払い、他者への影響を考慮しながら生きる必要があるのだろう。
名前に思いを込めてしまった人間たち
自分の名前は自分で選ぶことができない。当たり前のことだが、ほとんどの人は両親に名前をつけてもらっている。近年、「キラキラネーム」が話題となった背景には、自らの名前に対するコンプレックスが影響しているのではないかと考えられる。自分の名前に納得がいかず、自分に子供ができた時にそのコンプレックスを解消しようとする親たちが、独特な名前をつけるようになったのかもしれない。
名前というものは、本来、他者と区別するための記号に過ぎないという考え方もある。人間は何事にも意味や感情を込めたがる生き物であり、子供の名前も例外ではない。親たちは、名前に対して「こう育ってほしい」「こういう人生を歩んでほしい」という願いを込めてしまう。この思いが強くなるあまり、独自性を求めた結果として「キラキラネーム」が生まれたのかもしれない。
一方、自分の名前にコンプレックスを抱く人々は、名前を単なる記号として捉えている可能性がある。名前が記号であるならば、よりかっこいい、可愛いものにしたいという考え方も理解できる。これは、名前の機能を他者との区別に限定し、そこに美的な要素を求めるという意味では、ある種の合理性を持つ考え方であるとも言える。
プロローグもエピローグも描けない私たち
始まりがあるということは、必然的に終わりがあるということでもある。人間は生まれた瞬間から、死という避けられない終わりに向かって進んでいる。どのような巡り合わせで生まれてきたのか、私たちは知ることができず、生まれること自体も選択できなかった。そして、死ぬ時期や状況もまた、自ら選択することはできない。私たちは、いつ死ぬか分からない状態で日々を過ごしている。
興味深いのは、死という絶対的な不幸が待っているにも関わらず、人間は日々の喜びや楽しみを享受し、笑い、喜び合うことができるという点である。もし、楽しいことや嬉しいことの度に「でもいつか死ぬんだけどね」と言い続けたら、私たちの生活は大きく変わってしまうだろう。このように、死を意識しすぎずに生きられるというのは、人間が持つ特異な能力であり、これを可能にした自然の仕組みは見事である。
一方で、私たちは日常の些細な不幸には非常に弱い。死という最大の不幸に対しては無視することができるのに、ちょっとした人間関係のトラブルや小さな不運には、心をかき乱され、夜も眠れないほど悩んでしまう。この矛盾は、人間がいかに複雑な存在であるかを物語っている。
死を意識せずに生きることで、日々の楽しみを満喫できる反面、日常の小さな問題には過度に反応してしまう。これこそが、人間の心の複雑さであり、またその脆さでもある。死という究極の終わりが常に背後にある中で、今を生きることに集中する能力を持つ一方で、私たちは日常の些細な困難にも敏感である。



コメント